
2025年度入試の試験問題はどのような傾向があったのでしょうか。
Qゼミ中学部入試分析室のスタッフが集合し、一斉に各教科の学力検査問題を解き、その特徴をまとめました。
中2生以下、これから高校受験をするみなさんの参考になればと思います。
英語
ポイント3つ
- 時間配分は普段から意識する
- 頭から順番通りに解く必要はない
- 英検準2級レベルの単語力は必須
 分析担当:鈴木 智志先生
分析担当:鈴木 智志先生
<総評>
全体を通して考察してみると昨年よりはやや易化したを思われます。
【リスニング】
出題形式、難易度は昨年とほぼ同じでした。(ウ)No.1の問題で2019が正答だと思い、そのあとに流れてくるone year laterを聞き逃した受験生は多いと思われます。リスニングは2回流れるので最後までしっかりと聴くことを意識しましょう。
【語彙・文法:問2~4】
出題形式に変更はありませんでしたが、昨年と同様に問2では教科書に出ていない単語が見られました。問3の(ア)では先頭にhaveがあるから現在完了と思い込み、takenを選ばせるミスリードを誘う問題で、正答は現在分詞takingでした。落ち着いて考えると正答できますが、時間配分が大事な科目だからこそ焦って間違った選択肢を選ぶと考えられます。問2.問3は昨年よりも少し難化しました。
【英作文:問5】
By~ingの答え方を見て、疑問詞のhowを使用して間接疑問文を作り、答える問題でした。上記の答え方は英検準2級の2次試験で扱いますので、英検準2級以上を取得している生徒は正答できたと思われます。
【読解分野:問6~8】
出題形式に変更もなく、全体的に解きやすい設問でした。
問6は話に共感できたからこそ理解できた受験生も多かったのではないでしょうか。問7は昨年より分量が減り、難しい単語も、ミスリードを誘う問題もなく、易化しました。
<これから受験をする生徒さんへ ずばり対策方法>
昨年から単語のレベルが上がり、教科書だけでは対応が難しいです。その場合積極的に英検準2級まで取得する必要があります。また中学3年生で勉強する単元が並び替えなど、多く出題されるので中学3年生の単元は完璧にしてから臨みたいです。今年度は問2~4が難問でしたので、順番通りに解かず、長文読解から解くのもありです。長文を解くときは常に時間を計ることを徹底しましょう。また、自分に合った英語の解き方は模試などをたくさん受験して、確立していきましょう。
国語
ポイント3つ
- 語彙と基礎知識(文法・漢字)の定着
- 抽象概念の読解力
- 身近な事象への関心度
 分析担当:畠中 真美先生
分析担当:畠中 真美先生
<総評>
2024年度の総文字数は18,381文字、2025年度は17,938文字でやや減少となりましたが、全国平均が9,000文字という中で約2倍の文字数が依然ある入試となりました。
傾向の変化としては論説文の文章中から文法問題と対義語の問題が出題されていました。
問1の漢字・鑑賞文
全体的に平易。漢字の基礎力がついていれば十分に解ける。ただし鑑賞文は若干、難しい。「左右なる」の意味が掴めない受験生がいたかもしれない。
問2の物語文
大人の目線から見た子どもの成長を通じて自己の再発見をする物語。会話も平易で読みやすく、素材文も短く難易度は低い。得点源にしたい問題だった。
問3の論説文
例年並みか若干難しく感じた受験生もいたはず。抽象的な文章なので、何となく読んでノリで解くことは不可能。読解の方法の基礎を身につけた上で、正確な文章理解の訓練を積むことが必要になる。併せてAIやVRの世界など、昨今は避けては通れない主題について日頃から関心のアンテナを立てておくことを勧める。どの科目も現代社会の問題や潮流を反映したうえで作問がなされている。
問4の古文
例年より読みやすく易しい。神奈川県の土地の支配に関する問題だったので、内容も歴史を学んでいる中3ならば理解しやすかったはず。
問5の記述
複数の文章を読んで記述する問題は、LINEと手紙という、よく出るコミュニケーションの方法と質に関する問題。スマートフォンがツールとして一般的な現代では頻出の主題であるため、受験生にも分かりやすかったはず。
全体的に難易度が下がった2025年入試ではないかと思われる。
<これから受験をする生徒さんへ ずばり対策方法>
漢字・文法・語彙。知識問題は、学習すれば確実に定着し、得点となりうる。
地道な学習を継続すること。
また、論説文は抽象的で難易度が下がる年はあまりないので読解の方法を理解したうえで多くの問題にあたり演習量を積むことをお勧めしたい。
そして何よりも、いま社会で何が起きているか、時代がどう動いているのか。
自分なりに、自分の生きる世界への興味関心を絶やさないことだ。
数学
ポイント3つ
- 出題傾向は例年と同じ
- 昨年と同様に思考力・総合力を必要とする問題が出題された
- 過去に出題された問題に則った対策ができたかが得点力の鍵だった
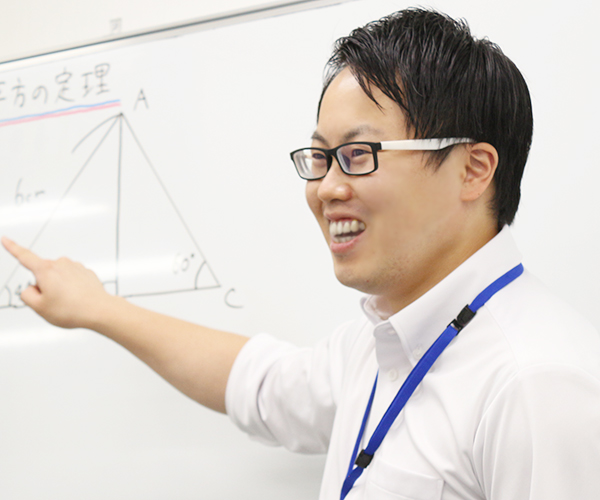
分析担当:馬場 翔吾先生
<総評>
全体的な出題傾向はほぼ昨年と同じであった。そのため昨年と同様、問1、2を全問正解することができれば、その時点で39点は確保できる。ただ6点配点の問題が1問増え、4問となりました。
問1、2については例年と同じ傾向の出題内容であり、難易度も昨年と同程度であった。
問3(ア)も例年と似たような内容の問題であったが、与えられた情報から図の中に正三角形などの特別な図形があることに気付けるかが鍵であった。 (イ)は例年通り箱ひげ図の問題が出題されたが、登場人物の会話文をもとに情報を整理するという点が例年と異なっていた。また(ウ)は図を見て2次方程式を立てて解くという問題が出題された。(エ)の求角の問題は、平行線から錯角・同位角を求め、正方形という辺の長さが等しい図形から、合同な三角形を見出せるかが解法の鍵であった。
問4(ア)・(イ)は例年通りの出題内容で、計算自体はそこまで複雑ではなかった。 (ウ)も難易度は例年通りであったが、解法の考え方は過去の入試問題に数問出題されたことがあるような内容だった。
問5は去年と同じ2つのさいころを使う問題であり、操作内容の複雑さも昨年と同程度だった。
問6(ア)は三角錐の表面積を求める基本問題だった。 (イ)は必要な面を自分で書き出し、体積から高さを逆算させる問題であった。
今年度も全学年の単元が満遍なく出題されており、一部思考力を要求する問題も出された。ただし、例年の過去問から大きく逸脱するような問題は出題されなかったため、いかに基礎力を高め、過去の出題問題に則った対策ができたかが得点力の鍵となるような内容であった。
<これから受験をする生徒さんへ ずばり対策方法>
今年も昨年と同じくらいの量の基本問題が出題されました。また、入試の傾向や難易度も例年と同じくらいとなっていました。そのため、次の入試対策は基本公式について反復練習を行い、しっかりと定着させることが重要です。その上で過去問も解いて、過去にどんな問題が出題されたか確認をしましょう。問題を解くときは「与えられたヒントにはどういう意味があるのか」を考えながら解くことで、より高い思考力を養っていくことができるでしょう。
理科
ポイント3つ
- 物理・化学・生物・地学 各25点ずつの配点
- 難易度はやや難化
- 学年配当に偏りがある(今年は中3からの出題が多かった)
 分析担当:伊沢 淳先生
分析担当:伊沢 淳先生
<総評>
昨年と傾向は変わらず4分野から均等に出題されています。
学年配当は中1から32点、中2から24点、中3から44点と偏りのある結果となりました、。また昨年から完答がなくなり小問ごとに配点がつくようになり、こちらの傾向も変わらずとなりました。難易度については昨年と比べるとやや難化したと思われます。
今年度は昨年と比べると大きな変更はほとんどありませんでしたが、問題としては基礎知識の重要性がさらに増したように思います。
小問1(ア)、小問2(ア)~(ウ)等の小問の中には光の屈折を図に書き込んで考える、実際に数字を入れて考えてみる、電離式を書く、イオンの数を実際に図として書き出してみる等、文章を図に表して視覚的な確認ができるような作業を行うことでミスを無くし確実に答えに結びつけられるような解き方ができる問題が増えたように思います。
大問の方では引き続き、実験や結果、観察内容を表や図から読み取る問題が出題されました。今年度は物理、生物、化学の3分野から出題されています。他の科目にも言えますが大学共通入試の影響で資料問題、考えさせる問題が増えています。思考力を問う問題が増えてはいますが、図や表から分かることを整理する力があれば余計な情報を省いて考えられます。複雑そうに見えるものも何を問われているかを簡略化して考えることが出来れば難易度はぐっと下がりますので整理する力も一緒に身に付けていきましょう。
<これから受験をする生徒さんへ ずばり対策方法>
近年の理科では単純な知識を問う問題は出題されません。むしろそのレベルの問題は解けて当たり前となります。今持っている知識をどう問題に生かすかという「思考力」が必要になりますので、前提となる基礎知識がまだ定着していない場合はまずそちらを固めましょう。その後、過去問や問題集などを通して実験・観察に関する文章題を解き、問題文を読み解く練習、整理する練習、そしてその知識をどう使うのかを考える練習を反復して力をつけていきましょう。
社会
ポイント3つ
- 教科書内容の基本的知識はしっかり押さえておこう(特に歴史・公民)。
- 知識の単純暗記でなく、自分で論理的に説明できるようにしよう。
- 統計資料を読んで、地理・歴史・公民の融合問題に対応しよう。

分析担当:高橋 秀幸先生
<総評>
■問1世界地理14点
(オ)で、2020年度以来の「時差」が出題されました。貿易や使用言語の資料から、かつての欧米諸国の植民地支配からの独立が出題テーマでした。資料の読み取りがポイントです。
■問2日本地理・地形図の読み取り15点
(ア)雨温図の読み取りは定番問題です。6気候区の降水量と気温の特徴と理由はつかんでおきましょう。津波の被災マップを読み取る問題、産業別就業者割合の資料から、地域をあてる問題など、グラフや統計資料を読む力が必要ですね。
■問3(近世までの歴史)・問4(近・現代史) 歴史30点
資料、史料がいつの時代のもので、選択肢に出てくる語句がいつの時代のものか、基本知識は時代別につかんでおきましょう。年代の記憶をしておくと、短時間で解答できます。
■問5公民(経済分野)15点 ※昨年14点
公立入試は、政治よりも経済に比重がおかれています。売買契約は売主の「売ろう」と買主の「買おう」という意思の合致で成立し、代金の支払いは契約の履行であり成立とは別問題だということは知っておきましょう。政府の行う財政政策(国債発行など)と日本銀行の行う金融政策(国債の売買)の違い、為替相場や景気変動、金融など、基本的な知識で対処できるが、円高・円安の影響や誰から誰にお金を貸すとどうなるのか、景気が悪いときに政府や日本銀行はどうするのかなど人に説明できるくらいに自分の頭で整理しよう。
■問6公民(政治分野・現代社会) 14点 ※昨年15点
(イ)議院内閣制、(ウ)人権、(エ)核拡散防止条約、(オ)話し合いにおける効率と公正など、かつての政治知識の出題のメインが集約されている感じです。条文読み取り問題は今年は出題されていません。
■問7地理・歴史・公民融合問題 13点
資料を読んで、計算が必要であれば計算し、知識が必要であれば知識を動員して解答する柔軟さが必要。
<これから受験をする生徒さんへ ずばり対策方法>
歴史の年代暗記や世界の気候区や日本の気候区などをふくめ基本的な知識は絶対に必要ですが、その知識を「知っている」では足りず、なぜそうなるかを自分なりに理解している必要があります。また、知識を応用するための「思考力」や「計算力」が必要になります。統計や資料を使った問題を、学校の定期テストなどで数多く触れ、その場で考えて解く練習をしましょう。神奈川県だけでなく、全国の入試問題を解くのも勉強になります。








